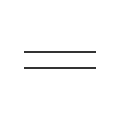取り組む課題
カンボジアでは病院の給食が患者の栄養を支えるものとはなっておらず、学校や孤児院などの施設でも、栄養の視点で給食を提供しているところはありません。
課題に取り組むことになった背景
アジア諸国の中で、子どもの栄養不良率が高い国の一つであるカンボジア。栄養に関する専門家は極めて少なく、これを体系的に教える教育機関もありません。そのため病院においても、患者に提供される給食は栄養の点での考慮が欠けており、患者の回復力を高められないために、病気やけがの治療効果があがりにくいという例も少なくありません。

FIDRは2006年4月から2014年3月までの8年間「国立小児病院給食支援プロジェクト」を実施して、国立小児病院(以下NPH)で栄養バランスの良い給食を提供できる施設と運営体制を確立することができました。しかし、患者の治療を受けもつ医師や看護師には、食事と栄養に関する理解に改善の余地があります。給食を通じた患者の栄養管理を実現するには、そうした人材の能力を着実に強化させることが欠かせません。

同様に、病院のみならず国内の子どもに給食を提供している学校や孤児院においても、栄養バランスを考慮した食事は職員の知識や技術の不足により実現できていません。そのためにNPHで確立した給食をモデルとして、それぞれの施設の給食を改善する必要があります。そうした取り組みを支えるためには栄養摂取に関する公的な基準が必要ですが、カンボジアにはまだ存在しません。現在、保健省は「子どもの栄養摂取基準」を制定する方向性を打ち出していますが、このための実務作業を進めるのに足りる能力をもった人材がいないという課題を抱えています。

FIDRが目指すもの
子どもに給食を提供する病院や施設において、子どもの栄養状態を正確に把握し、適切な食事の提供やケアができるようにします。
プロジェクト詳細
活動場所
プノンペン市 カンボジア国立小児病院および国内各地の子どもに給食を提供している施設
(病院・学校・孤児院など)
効果を受ける人たち
- 国立小児病院職員(医師、看護師、調理師):約350人
- カンボジア国内で子どもに給食を提供している施設の職員
- 国立小児病院入院患者(年間約10,000人)
- カンボジア国内で子どもに給食を提供している施設の子どもたち
現地で行う取り組み
- 国立小児病院における栄養管理の導入
- 子どもの食事摂取基準のための調査・策定
- 他施設における給食管理、栄養管理に関する指導
活動期間
2014年度~2018年度
FIDRのアプローチの特色
- カンボジアの子どもの栄養不良に対して、様々な機関が保護者への啓発活動や微量栄養素の配布などの取り組みを行っていますが、病院をはじめとする施設で提供される給食に栄養の視点が欠如していることに着目し、職員の知識や技術を向上させることで改善を図ります。
- 国立小児病院給食支援プロジェクトを通じて培った、現地の食材や食習慣、人々の技能に応じた給食改善の方策を、それぞれの施設の状況にあわせて工夫し効果的に導入できるようにします。
- カンボジアにおける子どもの食事摂取基準や指導要綱などを政府と共同で作成することで、子どもの栄養不良という問題への対策が全国規模で、永続的に行われるための基盤を固めます。